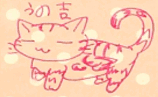第1楽章が長調なら、多くのケースで第2楽章は短調となるところだが、第11番では、第2楽章は引き続き長調で、のどかな雰囲気となっている。また第2楽章としては珍しくソナタ形式となっている。
青空を見上げるような爽やかなテーマが続く。
そして、そよ風のようなテーマで終始明い雰囲気が続く。
展開部は短調で開始し、最初のテーマが展開されていく。
再現部。
最後までのどかな雰囲気が続いて終わる。
楽譜引用はヘンレ版。
Apple Musicの方はこちら。
第11番は、元気の良い主題で始まる。
この曲も様々なテーマが次々と登場し、初期ソナタの代表作と言える。
どのテーマも明るい光に溢れている。
ここで少し落ち着く。
スケール主体の力いっぱいのテーマ。
展開部は最初のテーマで始まる。
展開部では、このテーマが繰り返し用いられる。
最初のテーマが再現されて終わる。
Apple Musicの方はこちら。
珍しくスケルツォが最終楽章に配置されている。新たな試みへの挑戦なのかもしれない。テーマはどれも即興的で素朴なものが活用されている。
最初のテーマはスケール主体で、次のテーマはアルペジオ主体。
民謡風なテーマが現れる。
ここもスケール主体の素朴なもの。
最後は、最初のテーマが再度現れて終わる。
楽譜引用はヘンレ版
Apple Musicの方はこちら。
なんとも、かわいらしい行進曲のような変奏曲。
最初のテーマと、次のこのテーマが変奏される。
ここから変奏。
最後は、最初のテーマがそのまま繰り返されて、少しおどけた感じで終わる。
楽譜引用はヘンレ版。
Apple Musicの方はこちらから。
家のオーディオ再生をRaspberry PIに変更してみた。
元々は、Apple TVにDACをつなぐ形にしていたのだが、Apple TVは、やはりApple縛りがキツく、音楽格納場所にMac母艦が必要だし、リモコンでの操作も面倒だしで、去年くらいにChromecast Audioに変更した。
Chromelcast Audioは、しばらくは調子が良かった。Spotifyの再生デバイスにもできるし、AndroidからでもMacからでもキャストできる。ただ、最近のAndroidのアップデートのせいなのか、再生中に頻繁にプチプチと途切れるようになってしまった。というわけで、色々調べてみると、Raspberry PIが良さげなので乗り換えてみることにした。
Raspberry Piは、Zero Wをスイッチ・サイエンスで購入。DACは、これを買ってみた。接続は、GPIOの線を数本接続するだけ(DACの販売ページに書かれている)。Raspberry PI Zeroの場合は電源は、GPIOから与えれば良いので、5V 1AのACアダプタで供給。
再生ソフトは、Volumioを使用。セットアップが面白くて、起動するとRaspberry PIがホットスポットとして上がるので、PCからそこに接続して設定できる。家のWifiの情報を設定した後、ホットスポット機能をoff(そうしないと、誰でも入れちゃう)。Zeroconfig対応なので、http://volumio.localでアクセスできるようになる。
うちはFreeNASを使っているので、VolumioからはNFSの設定をしてやれば、勝手に音楽ファイルを見つけてくれる。あとはPluginを入れてやれば、Spotifyにアクセス可能となり、Spotifyのプレイリストを再生したり、PCからSpotify出力デバイスとしてVolumioを使えるようになる。
正直、この価格帯のDACには期待していなかったのだけど(特にアナログの部分)、驚くほどクリアな音が出ている。Raspberry PIと同一の箱の中に収納したがノイズも全く聞こえないし、再生中にプチプチと途切れることもない。もう少し様子を見ないと楽観はできないが、今のところ好調だ。ちょっと心配なのは、Raspberry PIのSDがRead-only mountでないので、間違ってシャットダウンしないで電源抜くと再起不能になる可能性があることくらいか。
最近はやりの完全ワイヤレス・ヘッドホン。ちょっと興味があったので衝動買いしてみた。
apt-Xに対応していて音質の評価が高いものということで、ERATO Apollo7sを選択。
最初に良い点を挙げると、Bluetoothのヘッドホンとしては最高の音質だということと、やはりとり回しが非常に楽で、取り出し時にワイヤーが絡まっていて面倒ということもないし、社員証をネック・ストラップでぶら下げているような場合でもストレス無い。インターフェイスも良く練られていると思う。
反面、今ひとつかなと思うのは、電池が2時間くらいしかもたないこと、落としそうになること、あと持ち運び用のケースが充電を兼ねているのだけど、注意しないとズレて、うまく充電できていないことがある。音質は、あくまでBluetoothヘッドホンとして見れば良いということで、低域から中域の制動が甘く、割とボワボワした響き(サラウンドがデフォルトでonになっているので、切ると若干改善)。ただこのあたりは好き嫌いがありそう。SONYの普及価格帯のヘッドホンの鳴り方が好きな人は気に入るかもしれない。逆にモニタ・スピーカのような原音がそのまま鳴って欲しい人には向かないかもしれない。一応カナル型なのだが、ER-4Sなんかと比べると甘いので周囲の音が入りがちで、耳から抜けやすい。
音質が最重要であれば、このあたりのapt-X対応のアダプタに、自分のヘッドホンを接続した方がいいかもしれない。Apollo 7sの価値は、取り回しの楽さなのだ。
家のWifiルーターは、しばらくNuroから貸与されるものを使っていたのだけど、月に1度は電源off/onしないとおかしくなるし、同時接続数が10しかなくて辛すぎるので、交換することに。
Wifiルーターといえば、NECかバッファローというのが頭にはあったが、さすがにちょっと古い知識なので再度調査してみた。結局、国内メーカーのものは同時接続数が、20程度のものが多くて辛そう。今時、ラップトップに、タブレット、スマホに、スマートスピーカなど、同時接続数が10-20では心許ない。悩んだ末、TP-Link Archer C5400にした。中国のネットワーク機器は、セキュリティがどうのこうのという不安があるが、あれは、半分は米国の言いがかり的なところがありそうだし、世界的に見ると、このクラスではTP-LINKが圧倒的なシェアのようなので、何か変なことをすれば、すぐに大問題になるだろうということで割り切った。設定ツールが、しょぼくて初っ端から不安になったが、一度設定してしまえば特に問題も無く、去年末の入れ替えから安定、高速に動作している。
最初のアルバムが2014年なので、4年くらいかかったことになる。特に最後の30, 31, 32番は、なかなか満足行かなくて随分悩んだ。嬉しかったので、Spotifyで全曲プレイリストを作ってみた。
Spotifyのプレイリストは、同じアーティストだけの曲を集めることは推奨されていないけど、順位が下がるだけで他に弊害は無さそう。全曲聴いても、10時間あまりで、1日あれば聴けてしまうのだなぁ。
この曲も、様々なテーマが次々と登場する。
どのテーマも、ほのぼのとした暖かいもの。
1つ1つは違うテーマなのだが、雰囲気が非常に似ている。
展開部は、最初のテーマが短調で現れる。
様々なテーマが現れるこれまでの初期の作品とは異なり、展開部は基本的に提示部のテーマがきちんと展開される。
再現部は、一通り提示部の内容が繰り返された後、最初のテーマが再度現れて靜かに終わる。
楽譜引用はヘンレ版から。
Apple Musicの方はこちら。
即興的なロンド。単純なテーマが繰り返し用いられる。
雰囲気が変わってゆっくりとしたテーマが現れる。
ロンドとなっているが、多分にソナタ的で展開部は、このテーマが主に展開される。
再現部の最後に、最初のテーマが変化を伴って現れる。
楽譜引用はヘンレ版から。
Apple Musicの方はこちら。